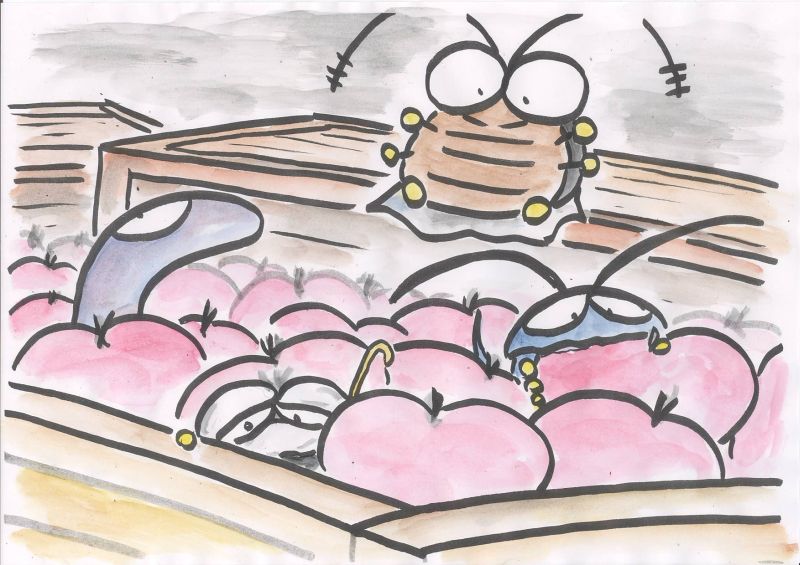 「今日もわれらムシのものがたりだ」
「今日もわれらムシのものがたりだ」
せっかくですので、今日もハチミツの話をします。今日の講義はなんと、李時珍先生に劣らぬ超有名人、明・崇禎の大博物学者・宋応星先生である。みな耳の穴かっぽじって有り難く聴くべし。
では、お願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○総論
凡醸蜜蜂、普天皆有。
およそ醸蜜の蜂は普天みな有り。
だいたい、ミツを貯めるハチは天下のどこに行ってもあるものである。
ただし、サトウキビ栽培の盛んな地域にはおのずとミツバチは少ないのである。
○蜜論
ハチの造るところのミツは
出山岩土穴者、十居其八、而人家招蜂造醸而割取者、十居其二也。
山岩土穴に出づるもの、十に居ることその八、而して人家の蜂を招きて造醸して割取するもの、十に居ることその二なり。
山中の岩や土の穴から採取されるのが十分の八、ニンゲンがハチに来ていただいて集め醸していただいたものの一部をいただくものが十分の二である。
(「招きて」の語感を生かして訳してみました。)
ミツには定まった色は無く、青かったり白かったり黄色かったり褐色であったりする。これらはその土地の花の性質によって変化するのである。例えば、野菜の花であるか、イネ科の花であるか、などによって相違し、種類を分ければ百にも千にもなるので、それぞれの色ごとに名をつけることはせず、すべてミツと呼ぶ。
○蜂王論
ハチには、ニンゲンの養殖するもの、野にあるものの別無く、蜂王があるものである。王の居所は、桃ぐらいの大きさの台状に造られた場所で、王の子が代々後を継ぐ。王は生まれながらにして花のミツを集める仕事はしない。ミツは、毎日その他のハチが輪番で班に分かれて採りに行くのである。
王毎日出遊両度。(春夏造蜜時)
王、毎日出遊すること両度なり。(春夏の蜜を造るの時なり)
王は、一日に二回、お出ましになる。(ただし、春から夏のミツの造成時のことである)
このとき、王の周りには八匹のハチが輪のようになって侍べる。蜂王は巣穴からお出ましになると、
四蜂以頭頂腹、四蜂傍翼飛翔。
四蜂は頭を以て腹を頂き、四蜂は翼に傍(よ)って飛翔す。
そのうち四匹が頭で王の腹の下を支え、残りの四匹が翼を支えて、飛ぶのである。
数刻にして巣穴に戻ってくるが、そのときも八匹が支えていること、出発時と同じである。
・・・「ほんとうですか?」
と訊きたくなってきますが、昨日の李時珍が「蜂の王は海の満潮干潮のときに合わせて出てくるのじゃ」といっていたのと比べるとより科学的であるといえよう。
○留意点1
さて、ハチを飼うときに気をつけねばいけないことがあるそうです。
「ハチを殺してはいかん、ということである。
ただし、
殺一蜂二蜂皆無恙。
一蜂二蜂を殺すはみな恙無し。
ハチの一匹二匹を殺すことは特に問題はない。
殺至三蜂群起螫人。
殺して三蜂に至るや群起して人を螫(さ)す。
三匹目を殺してしまうと、突如群れになってニンゲンを刺す。
これを「蜂反」(ハチの反乱)というのである。」
・・・「ほんとうに二匹まではいいのですか?」
と訊きたくなってきますが、「ではおまえ試してみろ」と言われるとイヤなので止めておきます。
○留意点2
ハチにも天敵がおる。ハチをよく養いミツをうまく集めるためには、天敵からハチを守ってやらねばならん。
蝙蝠最喜食蜂。
蝙蝠最も蜂を食らうことを喜ぶ。
ハチを最もよく食らう天敵はコウモリである。
巣箱の隙間からコウモリを投げ込んでみると、
呑噬無限。
呑噬無限なり。
口から飲み込むこと限り無い。
そこで、コウモリを殺してハチの巣の前に懸けておくと、「あのコウモリでさえ殺してしまうハチなのか」と怖れて、その巣箱のハチを捕食しにくるものがいなくなるのである。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このほか、ハチの分房の仕方、蜜を貯めるときにできる蜜脾というもの(昨日食べたのはこれであろう)が美味であること、ハチの子、黄蠟、山中のハチの集めた蜜の採取のしかたなど、たいへん役に立つ話が盛りだくさんでした。ああ有り難いお話だなあ。「天工開物」巻六・甘嗜篇より。
ちなみに、少年時代、歴史の授業で「テンコウカイブツ」という書名を聞いて「怪物」だと思いましたね。(今思うに「怪物」であっても博物学の書としては成り立ちうる気がするではないか。)
どなたかすごく有名な先生(小川環樹先生?)が幼いころ「南唐の後主」(李煜)という名を聞いて、「ばくぜんと女性であろうと想った」旨のことを書いておられるのを読んだ記憶がありますが、この先生の幼少期を取り巻く文化的環境が垣間見えて羨ましかったです。「カイブツ」を「怪物」と解するのもわしを取り巻く文化的環境の成せるわざであったといえよう。