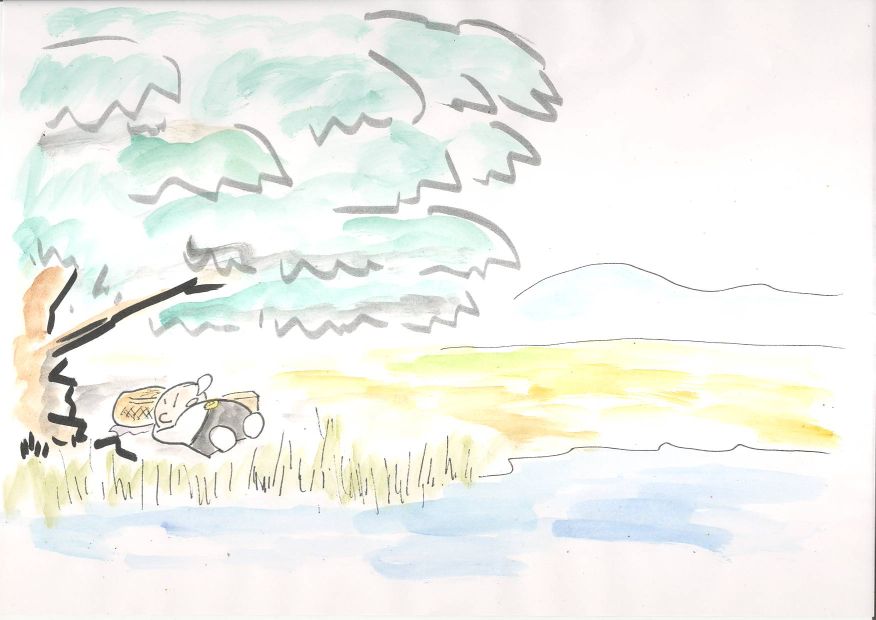
今日は新入りの本が入ったから、読んでみる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・わたしの幼いころ住んでいた家は朝廷からお借りしたもので、北京・西華廠南門のそばにあった。
当時はまだ北京市内にも家が建てこんでおらず、疎林や草地、小さな沼をなした空き地があちこちにあり、我が家の東隣もまた、数本の低木の生えた草っ原になっていた。
この空き地で、
毎夜犬吠不止。
毎夜犬吠えて止まず。
毎晩、野良イヌらしきものがこの空き地で吠え続けるのであった。
その晩もイヌの吠え声が聞こえ、わたしが眠られずに庭に出てみると、使用人たちも寝つかれぬものとみえて起き出してきていた。
わたしが庭を出たときは、ちょうど使用人頭の楊騒達がその子に命じて、境になっている垣根にハシゴをかけて外を覗かせているところであった。
楊は
「ぼっちゃん、何があるかわかりません、おうちに入っていておくんなさい」
とわたしを抱き上げて、わたしを乳母に手渡してくれた。
そのときわたしは別に怖がってはいなかったのだが、乳母はわたしに
「みなが守っていますから、この世の中にもこの世の外にも、ぼっちゃんが怖れることは何一つございません」
と言うてくれたものであった。
やがて楊の息子が降りてきて、言うに、
「空き地の中に
火光熒然。
火光熒然たり。
炎のような光が、ぼんやりと立っているところがございます。
イヌどもはここに向かって吠えたてているようです」
と。わたしは乳母の胸の中で、闇の中に青白い炎が燃えているのを想像して、その不思議な光景に心が躍ったのを覚えている。
「一体何であろうか」
「おそろしい妖かしではないか」
という者もいたが、わたしは、乳母に
以為財也。
おもえらく財たらん。
「おそらく宝物が埋まっているんじゃないかな」
と言うたはずだ。
やがて、父も起き出してきて、楊から報告を聞いていた。
父はもとより武人であるから、報告を聴くだけでは飽き足らなかったのであろう、自らまだ掛けられていたハシゴに登り、塀の上から隣の空き地を見た。やがて降りてくると、
此青燐也、何怪焉。
これ青燐なり、何ぞ怪しまん。
「青い燐火ではないか。少しも不思議なものではないぞ。
要らぬことで騒ぎ立てるでない!」
と家人たちを叱りつけたのであった。
これでとりあえず騒ぎは収まった。
しかし、余人の寝静まった後、楊は
「だんなさまはああ仰っしゃったが、いかなる妖かしとも知れず、我が家に禍を為さぬとも限らぬ。いったい何物かしかと見届けておく必要がある」
と言うてその息子とともにひそかに塀を越えて隣地に降り、
堀地三尺、果得枯骨一具。
地を掘ること三尺、果たして枯骨一具を得たり。
光の立ち上る場所を掘ってみたところ、地面から三尺ほど掘り下げたところで、ちょうど一人分の白骨化した死体が出てきたのであった。
父は、
知之大笑。
これを知りて大笑す。
そのことを聞いて、大笑いした。
そして、
「ほうれ、言うたとおりじゃ。青燐は戦地では多く見た。死びとのあるところに出るもので、何の不思議も無いわ」
と言うた。それから真顔に戻ると、
「どこの誰のむくろかは知らぬが、明末のどさくさでそのようなことになったのであろう。隣地に住んだのも何かの縁ではないか」
と、楊に命じて
令買棺盛之、移瘞野外。
棺を買いてこれを盛らしめ、野外に移瘞せり。
棺おけを買ってきてその白骨を納め、郊外の墓地に埋めなおさせたのであった。
後遂寂然。
後ついに寂然たり。
その後、特に変わったことはない。
ただ、わたしは、あのときの乳母の
「みなが守っていますから、この世の中にもこの世の外にも、ぼっちゃんが怖れることは何一つございません」
という断言を、ことあるごとに思い出す。それは今に至るまで、わたしの守りの言葉になっているから。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
清・劉廷璣「在園雑志」巻四より。
おやじかっこいいですね。
劉廷璣は字を玉衡といい、自ら在園先生、あるいは葛荘先生と号した。鑲紅旗漢軍に属する漢人貴族で、その祖先は遼陽のひとであるという。生年・卒年ともに不明だが、康煕五十四年(1715)の「春の初め」に「在園雑志」の自序を書いており、またそのときには「三十年官界にあった」といっているから、既に老年に達していたのだろうと思われる。「在園雑志」には、文字通り雑多な、官界時代の記憶、文学・歴史学に関するメモ、自らの見聞した奇事などが志されており、面白い・・・記事もあります。全部が全部面白いわけでもないです。